東京地下鉄の駅名です。はじめは単にそう思っていました。東京に出かけるとき、泊るホテルへいくときは茅場町を利用していました。地理感覚は全くなく、夜にホテルに入る時、200メートルの距離をタクシーを使ったこともあります。最近利用する地下鉄を変えてみました。水天宮という駅の利用です。何回か使っていて、水天宮という社(やしろ)が見え、好奇心で中に入っていくと子供連れの家族が多いのに驚きました。なんと子宝に恵まれますようとか安産を願う御宮さんだったのです。調べてみたらこのたぐいの御宮さんは全国にありました。子供連れが多いのはそのお礼なのかもしれません。こま犬の人形がたくさん飾っていました。このような風景を見ると何か昔ながら神を信じ、神を祈る姿勢に心うたれます。そういえば京都にある北野神社は受験生がわらをもつかむ気持ちでお参りするところでした。今週の学院のカリキュラムは「月の礼拝」です。単なる連続ポーズですが生きる日常から祈りを主とする生かされていることを実感するひとときです。

「うんちく・小ネタ」カテゴリーアーカイブ
断捨離ってなに?
先日の合宿の時に講師が断捨離という言葉を発せられ、当学院の受講生がそれを聞いて後日、あの「だんしゃり」ってなんですか、と聞いてきました。
その講師は「断捨離のすすめ」という本がよく売れている、あの本は整理整頓する方法を仏教の言葉で上手に本の書名にしたものだ、ヨガの中でプラティヤハラという段階があるが心の執着をとるために断捨離が必要だ、という内容でした。
私の身の回りには物にしろ、情報にしろ溢れています。ほっとくと物であれば「ゴミ屋敷」になるし情報であれば「自称評論家」になりひいてはノイローゼーになってしまいます。中村天風師の本を読むと、インドのヨガ部落で修業しているときに「文明人の理屈の多い頭をからっぽにしないければ何を教えても無駄だ」と言われるところがあります。映画「アバター」の中でも自然の中で生きている惑星人が地球人に向かって「頭をからっぽにしなければ自然の神から何も教えを得ることはできない」というような場面がありました。
私たちの生活は物欲、名誉欲、金欲、欲、欲ときりがありません。この欲のコントロールをするのがプラティヤハラ(制感自律訓練行法)です。詳しくは当学院hpに少しだけ書きました。
http://www.mizunoyoga.com/gakuin/q23.htm#l121
ところでヨガのポーズを作っているときに、できない、痛いは日常茶飯事ですが、できるときには突然できると様々なところでのべています。工夫と努力は当然大切ですが、痛みを我慢するという、とらわれや、ポーズを作ろうという気持ちが執着が欲につながってきているのです。頭をからっぽにしてただその場その場を感覚を受け入れていくしぐさこそがポーズであり、そのようなときになると瞑想になっていきます。そしてそのようなときに、こちらから思い追い求めていた対象が向こうからやってくるのです。求めているものを断つ、捨てる、離れるという断捨離は言葉で言えるほど簡単なことではありません。断捨離という思いこそが欲になってしまうのです。
それで数年前面白い体験をしました。我が家のリフォームの際です。家を片づけなければなりませんのでいらないものを捨てているとこの捨てるという作業が楽しくなってきました。来週の大型ごみの日に向かって、毎日小さな家の中を探索しています。何か捨てるものないか、いらない、いらないを繰り返し身軽になったわが持ち物に満足していました。ところがリフォームも終わり数年経ちました。また物が増え始めてきました。あれほどすっきりしていた家の中も見苦しくなってきました。これを見ても捨てるというのは癖です。またため込むというのも癖です。身一つで雲水のごとく、インドのサドゥのごとく生きることが一番の幸せかもしれません。
 マズロー欲求階層説から抜粋
マズロー欲求階層説から抜粋
 出典絵葉書
出典絵葉書
頼先生のアサナ指導
先日の登別合宿研修会の際に台湾ヨガ会の事務長「頼玉秋」先生のアサナ指導がありました。流れるような動きです。見ているだけでは何の変哲もないアサナですがこの一部の動きをしただけで、驚きの結果が生まれました。
まず私自身ですが、この後、前後開脚のポーズ、いわゆるハヌマーンアサナを行いました。私はこのポーズは不得手です。普段は痛い、伸びない、尻が落ちない、体全体が緊張に包まれます。しかしこの時は違いました。なんのストレスもなく、足は開きます。しっかりと胸の前で合掌できます。手を上に上げることもできます。140人の内の部屋の一角は私への拍手に包まれました。すごいすごい、瞬間です。今までのあの痛さは錯覚だったのか。体の条件が満たされると瞬間に可能になる事実の再現です。少しずつできるようになるのではなく、突然にできるのです。
それは合宿後、数日を経て教室で再現してみました。私のクラスは体の固い人ばかりです。教室は壁が少ないので二人組を作り、背中を借りて同じ動作を行います。そして開脚前屈のポーズを挑戦しました。10数人中90%の人が格段とポーズが進歩していました。腰がしっかり入っているのです。
いつも言っていることですが、腰を緩めるポイントはそけい部を締めること、胸を開くことであることがよくわかりました。そして動きの中で腸骨を回転するように行うことが大切です。この回転という動作は締めて緩めてという複雑な動き、協調が必要な動きでもあります。
「rai_T_asana.m4v」をダウンロード

医療類似行為について
新聞記事に人気の整体師が逮捕されたことが出ていました。私たちヨガ関係者も健康問題を扱う上でしっかりと記憶に残しておく必要があります。すなわち○○が直るという言葉は医療行為になります。言葉は微妙で自然治癒力を前面にもってくるのなら問題がないそうです。
前に社団法人○○会で治療師という名称で資格認定講習を受けたことがあります。この時はその医療類似行為についてかなり詳しくしつこく、授業を受けた記憶があります。現在、医師以外で医療行為ができる資格は医療類似行為と言われ、はあき法で厳しく行為を制限されています。はあき法とはあんま、マッサージ、鍼灸、指圧などの有資格者が守らなければならない法律です。その資格を持っていれば皮膚に鍼や灸で傷つけることを許され、治療目的でマッサージ、指圧ができるのです。
しかし、ここで職業選択の自由と言う憲法上の問題がでて最高裁判所まで持ち込まれ最終的に人の健康に害を及ぼさなければ誰でもよいというところに落ち着いたそうです。この判例によって今や整体師などの無資格の業者が増えてきました。
考えてみたらヨガの関係者も同じです。どうしても不調を訴える受講生、それに対処する行為は医療類似行為なのです。今回の新聞記事に取り上げられているのは治療行為の上、けがをしたという点です。この辺も微妙な問題を含んでいますが無資格者というマイナス面だけでなく、営業に力が入って、直す、直るという言葉を繰り返し行うことで医療行為と見なされたのかもしれません。健康増進という社会貢献を生業としている人は多くなりましたが、貢献と同時に無秩序ではないということを肝に銘じなければなりません。この業界の最高峰に位置する医師とて、やり方によっては傷害罪を適用される世の中です。この生業の中にいる私たちはしっかりと受講生とコミュニケーションを取り、言葉に気をつけてお仕事に励まなければなりません。そして調子が悪いときは病院へ行きなさい、自分で回復することができるのならヨガをしなさいとアドバイスしています。

他山の石にしたいものです。
親鸞上人
五木寛之作「親鸞」読み始めました。前に丹羽文雄作を読んで当hpの「最近のレッスン」にも取り上げました。(http://www.mizunoyoga.com/gakuin/q23.htm#l134)どちらも小説だから伝記の切り口がずいぶん変わるものです。読みやすいのは圧倒的五木寛之作ですが、親鸞の考えをもっと知りたいと思うのは丹羽文雄作です。丹羽文雄は浄土真宗の僧侶だから当然と言えば当然なわけです。昨秋に空海さんの高野山へ行きました。和歌山県の山の中なのに何か明るい景色が印象深いのですが、比叡の山は京都に近いのに何か暗い感じがします。高野山と比叡山は当時、宗教界の巨頭、空海、最澄が同時に生きた時代の山です。共に密教として修業のお山でした。しかしその後の偉人を輩出したのは比叡のお山で道元、栄西、日蓮ほかでした。最澄の教えには世の中を変えていく要素があるのだと思いました。
私が読んだ両著のキーワードは「地獄」だと思います。平安末期の混乱時代かもしれませんが、その「地獄」という言葉は「罰が当たる」と言葉を変えてと近世まで続きました。死ぬことの恐ろしさです。誰もが長い人生の中で後ろめたい言動があったから、浄土、天国に行けないのです。キリスト教に似ています。だから親鸞は祈り、宗教心を高めたのでしょう。浄土に行けるように南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えたのです。
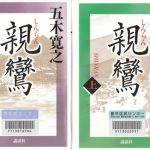
野球選手や芸能人もヨガ道場に来ていました。
これは最近友人に見せてもらった新聞記事です。東野修元監督、元西武ライオンズ投手の若かりし頃沖ヨガ修道場で2週間、修行したという記事内容です。東尾元監督が修行した昭和45年頃は沖先生も50歳くらいだからバリバリの現役だったのでしょう。私は52年だからこの頃でもかなりハードでした。朝6時の起床でお経を読み、マラソンと称して山の中を走りました。滝のコースではこの記事にあるように滝行もありました。みそ汁だけの朝食と昼は玄米ご飯、夜はそばと同じです。彼らは山を下りてパンを買ったそうですが、私は道場関係者のアパートに駆け込んでインスタントラーメンを他の人に見つからないように立ち食いしました。うまかったことこの上なしでした。しかし、自然食の純粋系の体になっていたため、じんましんが体中に出てかゆくて大騒ぎになりました。今はこの道場はないのです。現在、「沖ヨガの継承と後継者の育成」を標語にNPO法人国際総合ヨガ協会が各地で活動しています。

すぐれもの肩こり解消グッズ
軽くて楽な動きがいい動き
「軽くて楽な動きがいい動き」の標語でヨガ指導をしていますが、その原点はたくさんありますが操体法という治療法が一番初めだったと思います。操体法で検索するとたくさんの本と治療院がでてきますが、当時はまだ創始者の橋本敬三先生が存命中で私の周りはずいぶん騒ぎ、、彼らからいろいろ教わりました。
今、学院ではカリキュラムに入って体を柔らかくリラックスするテクニックで行っています。しかし数週間前からスタッフから火がついて、操体法のことをいろいろ勉強しだしました。私は本格的な操体法を10年以上やっていなくて、すっかり錆びついて、新たに勉強しなおしです。調べてみると本もたくさん出ているのに驚きました。しかし札幌市内で操体法をしている治療院を探したのですが、メインでやっているところはほとんどありません。なぜないのでしょう。この操体法は入口が広く、とっつきやすく誰でも出来そうな療法ですが、奥が限りなく深くそこに到達するのは並大抵ではありません。私が思うのにヨガと同じで学び続けなければ、マンネリになり技術が低下していくのです。それで操体法を取り入れていた治療院は他の療法と組み合わせて操体法を補助的にしか使わなくなったのかと思います。
ヨガの授業のときに、私は体のバランスや修正的なことはあまりやりませんでした。それはリラクセーションと左右対象のヨガポーズでまかなえると思っていたからですが、しかし今は少し考えを変えて、積極的に操体法とりいれた修正ポーズも行うことにします。取り入れて数日しかたって立っていませんが、基本操法(重心のかけ方、あしぶみ)をするだけで木のポーズや英雄の3番というバランスポーズが劇的に楽になるのです。

windows7に変更
昨秋から6年使ったwinxpの調子が悪くて、遅い、止まる、動かないなどで再インストールを繰り返していました。ようやくあちこちの家電量販店のDOSVコーナーで聞きまくってwin7 professional,Core i7 860 64bitを手に入れました。かなりのすぐれものらしいですがこちらの実力とソフトが不在なのでどこまでできるかわかりません。今回はぜひビデオ編集にチャレンジしたいものです。ところでこのパソコンは自作ですが、全部ショップの人にタダで作ってもらいました。内容は言いなりだったのですがマニアでないから言われもわかりません。電源は550Wですが他ショップによっては650Wまで積みなさいと言います。まえのXPは350Wですから進歩しました。ほかにもグラフィックボードは少し性能がいいのです。でもこの類は5万も6万もするのがあるそうです。とてもとても手が出ません。それこそ何に使うのと聞いたらゲーム関係だそうです。そういうものは一切やりません。他にHDDは1T、メモリー4GBなどで大台ちょっとだから安い買い物です。ということでお仕事がんばりまーす。





