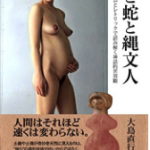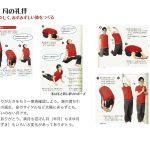私は朝は早起きです。夜はテレビを見ることが少なくなったのでしょうか、早く寝ます。いや年老いたからでしょう。
いつもと同じに早く起きて、何気なく古い辞書を手に取りました。中から黄色くなった新聞の切り抜きとメモがパサリと落ち、しみじみと眺めていると、遠い昔が思い出されます。それは1967年の高校卒業式のメモとその説明の記事でした。その記事は後年ですが、メモの意味がよくわかります。
そのメモと記事には「時代考験青年_青年創造時代」と書いてあり、台北市のレンガ壁の落書きだそうです。漢字の国らしく深い意味が当時の、この国に置かれた事情を表しています。
「歴史の大転進期に直面している現代は青年を厳しく試験し、激しく追求している。果たして彼らが、時代の試練に耐え、その要請に応えうる実力を養いそだてつつありや否やと。他方、青年には明日の世界を開拓して、一段と人類社会の進化発展に寄与すべき責任が現存する、明日の時代は、今日の青年が想像する責任がある、義務がある。」
と、記事の中で筆者が解釈をしています。
今21世紀の現代の中で、新型コロナウィルスの大きな問題、そして新たな香港問題、まだまだくすぶっている、中国・台湾問題。これらは50年前とほとんど変わらないことに驚きです。今やコロナ問題が余計に加わって、ますます、人間とは社会とは経済とはと考えなければならないことが山盛りです。その中で当時のような青年のエネルギーが少なくなってきているような気がします。
安保時代の私にとって、当時は青年たちが社会に働きかける機運が多くありましたが今は何か寂しい気持ちです。青年が頑張っているのが香港だけです。
ちなみにこの作者 湯浅八郎さんは当時、京都市教育委員長として高校の卒業式に来賓挨拶に来られました。湯浅八郎さんは長く同志社大学の総長を務められ、この記事からもわかるように国際基督教大学を創始され初代総長にもなった人です。
朝のひと時、とても気持ちのいい時間を過ごしました。
・・書いていて、あれ、どこかでこれ書いたことあるな、と思い、このブログを「時代考験青年」で検索してみたら、「2009.04.09」にありました。関心があれば読んでください。
最後に湯浅八郎さんのこと調べていたら以下の詩がありました。とても深く感銘を受けましたので、ここに記させていただきます。
湯浅は自身の生活信条を表す言葉として、次のような言葉を残した。
「 生きることは愛すること
愛することは理解すること
理解することは赦すこと
赦すことは赦されること
赦されることは救われること」
ーーーーー