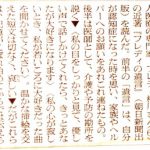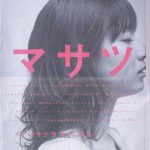WBCはすごかったですね。ヨガはさまざなところから学びに取り入れることが大切です。今回はイチロー語録です。「キューバ、韓国のユニフォームを着、ようやくジャパンのユニフォームを着ることができました。そしておいしいところだけをいただきました。ゴチソウサマ。」
感覚、感じを言葉にできるヒトはあまりいないですね。それも伝えられる言葉でね。言葉は共有するものですからね。ヨガ指導のときのほとんどは指示語です。足を延ばして、体をねじって、後ろを見て・・というふうにです。または教えてヤルというように断定語です。これはここに効きます、とか。(本当か、うそを言うなよと、このフレーズを聞くと思ってしまいます。)
ポーズを作っているときはいろいろな感覚が現れてきているはずです。そしてそれが感じや気持ちになっています。この感覚を共有したいのです。そのためには言葉が必要です。擬音でもいいです。イテテ、スーゥ、ンーム・・あまりぱっとしないけど少しはましでしょう。
イチロー語録みたいにはいかないけど、何か言葉がほしいです。筋肉をかき分けていくと、すごく怒っている部分があります。そこをなだめるのです。やさしく、感謝し、自分の傲慢さを懺悔するあやまるとかとかです。そんわけのわからないことをいつも言っているのですが聞いてくれている人もいるのです。教室全体が何か変わっていくといいと思いながら。
動物も感覚や感情を持っています。しかし彼らは言葉を持っていないために、自他に伝達できません。それで本能のまま、または学習したまま行動しています。そして自分をコントロールすることができません。人の素晴らしいところはコントロールできること、いやなことを快に変える能力を持っているのです。その道具はコ・ト・バです。