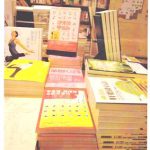朝は少し雨が降りそうだったのですが、天気予報などから昼近くになると、晴れる!という確証で開催しました。おかげで芝生の湿りもなく、快適な青空ヨガの開催日になりました。
毎年と同じように、たくさんの方が参加され、短い時間でしたが大いに楽しんでもらえたと思います。
毎年、必ず参加される方、ありがとうございます。その中には84歳になる方もおられます。また今回、妊婦さんで10カ月になる方も参加いたいだきました。子連れ、ご夫婦、親子三代、たくさんのありがとうで終わりました。

投稿者「mizuno」のアーカイブ
琵琶湖合宿
私の出身校、沖ヨガ道場の教えを後世に残すためのNPO沖ヨガ協会の定期合宿が琵琶湖湖畔でありました。
JR唐崎下車のKKRホテルびわこは景色もいいし、食事も抜群でした。ベジタリアン用と普通食を希望者毎にかえてもらったのは細やかなサービスです。
私にとって、琵琶湖は小さい頃、町内会からバスで真野というところで海水浴に行った思い出のある場所です。当時は海よりも琵琶湖で泳ぐことがほとんどで、ここで泳ぎを覚えた場所でもあります。子供の頃ですから大きな海のような存在でした。水もきっときれいだったと思います。
しかし今回は南の端の方でもあり、対岸のネオンがしっかり見えたりしてだいぶ、印象は違います。
しかし景観は写真のように抜群でした。


唐崎神社で朝の行法です。気持ちのいい日曜日が始まります。この神社は近江八景の一つになっていて、ここの松が金沢の兼六園に一部移したとのことです。美しい女性が近江富士を腕の間にはさんで二人ポーズです。絵になっています。この女性たち、実は孫がいる・・との噂です。へーぇ・・

さて今回合宿のメインゲストは「高野孝子」さん。文化人類学者で世界の民族の生活を研究されています。また各国の研究者と一緒に北極圏を横断したりする探検家でもあります。彼女は「生きること」をテーマに20歳前後の青少年を未開の土地に連れて行って生きることの基本を教える合宿活動もされています。

彼女の講義録を一部紹介したいと思います。
生きることに直結した暮らし
人として必要なことは自然が全部教えてくれる
土地とのつながりを取り戻す試み
大切なことってだっけ
幸せって何だろう
学校ではしばられたせいかつをしているけれど、雪山で解放された
いつもの生活が、どれだけ裕福で幸せなかを知りました
1日目緊張で話せなかったけれど、やっているうちに話せるようになってよかったなぁ
復興とはどこへ向かうことなのか、人が生き
るとはどういうことなのか。よくわからなく
なっていました。しかしヤップにはそれこそ
人が「生きる」現場がありました。無いことを
憂いて、なにかによって幸せになるのではな
く、知恵を出し、手をかけることでかぎられた
ものから豊かな暮らしを抽出するような・・そ
のプロセスの中で心も身体も動き出して、
人が本能的に持っている躍動感を楽しめて
いるような気がしました。逆に言うと、近代
的な生活は、その喜びを奪っているんだ
なぁ、という感覚も感じました。

前列左端、私はカメラマン。
心の成長を支援するセミナーを受講して

私は本屋やネットなどで「コーチング」という名前は知っていました。しかしそれは自己啓発セミナーの一種だと思う程度でした。そしてまた、一昔前はそのようなイベントがたくさんありました。その当時の内容は玉石混合でした。
しかし今回は講師が長く水野ヨガ学院に来られている方であり、熱心にカウンセリングの勉強をされ、たくさんの資格を取得されていることもあって、雑談を交えて心の在り方をよく話をしたり、教えられたりしていました。
ヨガと心の関係はとても大切なことであり、沖正弘師はヨガを菩薩行と言われたくらいです。
講師と話していて、現代の八方ふさがりの中、まだまだ自ら不幸せを演じる人が多いことを知らされ、私自身の学びにもぜひコーチングセミナーを開催してもらうように依頼しました。
私が思うのに、今の世の中は人間関係が希薄、高度に発達した管理社会、利益優先の社会、差別社会の出現などこれからも大変な社会の中で私たちは生きることを強いられています。私がヨガに関わった30年、40年前の時代は高度成長時代の社会の変革期でした。おそらく現代はそれ以上に社会不安や不景気、世界のグローバル化などが相まってより厳しいかもしれません。
しかし自分の心を正面からとらえて、ものの見方を変え、気づきによって「ネガティブ思考を解放することができる」ことはそれほど難しくないみたいですし、そのためには不幸を演じる癖直しが一番大切なことだと思います。
授業の概要は以下のように進みました。
それぞれが自己紹介をしました。参加した目的などを話してもらいました。そして講師はコーチングの基本を説明しましたが、講師は特に説教的な話はなく、人の話を聞いてください。そして自分のいいところを話してください。 また自分はどれだか周りから支えられているかを話してください。人の話を聞き、又感銘を受けた時は拍手してください。というコメント程度です。
次に物語を読んで「この人の一日はどうとらえますか」ということを自分の考えを話してくださいと提案です。
簡単に物語を再現してみると以下のようになります。
久しぶりの友人に会うため札幌駅の地下にある店で13時に会う約束をした。土曜日に会うことを心待ちにしたが地下鉄は事故らしく途中で止まってしまった。自宅から地下鉄駅に向かうとき知り合いのおばあさんの大きな荷物を持ったため、時間は遅れ気味であった。電車が一本早かったら事故に遭わなかったかもしれない。
途中の駅を出てタクシー乗り場に行ったが雨が降っていて乗り場は混雑していた。友人に前に会ったときは携帯が無かったので待ち合わせ場所がわからないこともあり1時間もかかったことを思いだす。家を出るとき家人に傘を持っていくように言われて持ってきたことはラッキーだった。傘をさしてタクシーを待つ。友人には遅れることを連絡した。そのうちに携帯に登録していた交通情報サービスの配信で地下鉄が開通した連絡を受けた。タクシーに乗らないで地下鉄に戻って札幌駅に着く。20分くらい遅れた。途中で急いで走ったので足をひねってしまって転倒した。すごい痛みで歩くことはできない。近くにドラッグストアがあった。見知らぬ人が肩を貸してくれて連れて行ってくれた。湿布して薬も飲むが痛みが治まらないので、友人にドラッグストアまで来てもらう。彼と話をして病院へ行くことにした。開いている病院をドラッグストアの店員に聞いて、友人の肩につかまりながら病院へ行くが医者に骨にはひびがはいっていないといわれて安心した。夜の10時までレストランや喫茶店で話をした。友人と話してストレスも発散した感じだ。夜には病院からもらった痛み止めのせいか痛みもなくなっていた。
今日はどんな日だったかと思いだした。
「幸せ・不幸せ」を参加者全員でいろいろな面から話を出しました。初めは不幸と思っていたことが実はそうではなく、表裏一体なのだということに気がつかせ立という意見に終始しました。たとえばケガをしたけれど、親切な人に助けられたり、薬局が近くにあったり、土曜日に病院があったり、骨が折れていなかったり、充実した友人との会話であったことなどは見るところがどこなのかによって気付きが異なってくるという内容です。
このセミナーは教えてもらうセミナーではなく、自分が発言して気がつき、そして他の人の発言で、また気がつくというセミナーでした。講師はほとんど講義らしいことはしないことが特徴でした。
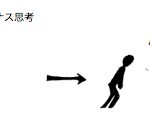
このセミナーは幸せ・不幸は表裏一体であることに気がつくことで、「ネガティブ思考」の手放し方は意外に簡単だと気がつくという趣向でした。
最後に講師は以下の宿題を2週間行ってくださいことを受講生に依頼されました。思考の癖を直すには2週間という時間が必要だそうです。
「毎日自分をほめる」 (それは自分への信頼感です。)
「毎日自分は支えられている」 (それは周りへの信頼感です。)
これからもこの2点を毎日問い続けてください。それは自分がネガティブ思考を手放す癖がついたときに幸せアップになることです、というところでセミナーは終わりました。
一人だけの桜
今年も近くの林業試験場(農水省管轄)に桜が咲きました。今年は雨が降って、どうなることやと思っていましたが、きれいな豪華な桜並木になりました。テレビ放映されたのか、たくさんの見学者で有名になりました。最近は車乗り入れ禁止です。数人のガードマンまで立っています。
日曜日には我が家の前の道路は片側にずらりと駐車です。曇り空にもめげずに、たくさんの人が行き来しています。桜並木がどこかの行楽地のようです。その中に見覚えのある人が。。やぁやぁとしばらく立ち話でした。お茶でもどうぞとしきりにさそったのですが、いえいえまた今度ということでした。(これ断られたのですね。遠慮したのかな。)
二日後、今日の朝は抜群の天気です。カメラを持ってもう一度桜の見学しました。誰もいません。すごいことです。
誰もいない自分だけの桜の中で写真を撮りました。駐車禁止の赤いコーンが邪魔です。

価値あることだけどちょっと恥ずかしい
笑いヨガがずいぶん普及しています。40年以上前から沖ヨガの創始者沖先生はヨガの授業でほとんど毎日、「笑いの行法(ぎょうほう)」を行っていました。「笑ってみろ。」「もっと気分よく笑え。」などと夜の寝る前にそんな授業をやりました。今では、私も教室でも私的生活でも笑っているのですが、場所が限定されます。お風呂の中、車の中、誰もいないところですが、最近、街中でも歩きながら「くっくっ」と笑うことがあります。特別大きなアクションさえしなければ誰も気がつきません。どうぞ、リフレッシュするために、気分転換のためにみな様も「くっくっ」と笑ってみませんか。
笑っていて気がつくことは、普段の感情というか、思いというかどこから湧いてくるのか不思議に思います。例えば困ったことや不安なこと、怒り、悲しさなどの感情が湧くとき、その感情は繰り返していると、深くなって、そして気持ちが暗くなっていきます。それはエスカレートしていくのです。そこで気を取り直して「ワハハ」と小さく、数回笑うと、今までの暗い気持ちはどこかに行ってしまうことがよくあります。その気持ちはどこへ行ったのでしょうね。
ところが、ある人はそんな簡単に気分が変わらないとも言います。変わらないのは、その感情を思い出すからなのでしょう。思い出さなければいいのです。思い出すことをやめるのです。思い出そうとしたとき「グッバイ」と切り替えるのです。例えば、「次」と他のことを考えようとすればいい、これは少し練習も必要かもしれません。切り替えの上手な人はそのようにやっているのです。落ち込んだとき、「笑う→思い出さない→他のことを考える」ということをやって見る価値はあります。
その中で一番大切なことは、「くっくっ」と笑うことです。最近は街中でマスクをしている人が多くなりました。そのマスクのなかで「くっくっ」と笑ってもいいじゃありませんか。自分は他人が見えていても他人は誰も見ていないとわかったら「くっくっ」と笑います。お腹がちょっと痛いくらい「くっくっ」がいいでしょう。
次の話題です。
階段の降り方は前にこのブログでテーマにしていますがもう一度テーマにします。
先日、地下鉄の下りを若い男性が猛然と走っていきました。発車に間に合ったのでしょうか。面白かったのは彼の後ろ姿が「エリマキトカゲ」そっくりの走りでした。エリマキトカゲとはどんなのか写真でお見せします。


彼の手も足はまったく「エリマキトカゲ」です。でも上手にすばやく、降りてるなと感心しました。数段だけ私もやってみましたが、人の目があるのでやめておきました。その降り方は山の下りで、大きく横に飛んで左足で支え、また横に飛んで右足で支え、膝を大きく屈伸して、飛ぶように降りていく姿と同じです。ただ彼の腕は空身なのでバランスをとるために「阿波踊り」風でした。これは腰を柔らかく使っているので膝にもよさそうです。
は虫類は地上を這うしぐさしかできなかったのが、エリマキトカゲは進化して、地上を飛ぶように走ったのです。体の負担を最小限にするためにあのようなビデオの早回しの阿波踊りのような走りになったのです。私たちは手を上げなくてもいいのですが、膝を外に交互に出して降りると、まるで落ちるがごとく気持ちよく下ることができるでしょう。
ただし、転んでケガをしても自己責任なのでそのつもりでやって下さい。
アサナ写真集の更新
当学院では壁にアサナ写真集を掲示してあります。原則としてカリキュラムは3ヶ月毎に数年間、くりかえしていますが、今のところ不都合はありません。ヨガは変化刺激が大切ですから、前と同じ授業をしていません。絶えずもっといい動き、もっとわかりやすい説明、向上していくことを求めています。
今回も前のアサナと同じです。しかしモデルがかなり変わりました。変わらないで、前に撮らせていただいた方も少しは載せさせていただきました。いい写真がないので再登場をお願いしました。改めてお礼させていただきます。
今回の大きな違いはカラーになったことです。やはり華やかです。そして研究生だけでなく、受講生の方にも参加をお願いしました。美しい、きれいなポーズだけではありません。発展途上のポーズもあります。老若男女、そしてアクロバティックなポーズもあります。掲示して受講生の方の評判はよろしいようです。6年ぶりの更新です。更新にご協力いただいた皆さま、ありがとうございます。
手元の見過ぎ失敗を招く
新聞記事のタイトルです。記事の内容は難しそうですが、
ピアノの練習、バスケのドリブル、パソコンのタイピングなどは手元が見ない方が早く、上手にできるという内容です。
私にとってはどれも身に覚えがないのですが、なるほどと思いました。
ある人との話しで、年のせいか、駅の下りの階段で若い人に追い抜かれることが多くなった。
降りるのが遅くなったのは、転ばないように足下をいつも見ているからだという。
全く視線を外すことはできないが手すりを軽く持って、5〜6歩先を見ながら
降りていくと軽やかに降りることができるとのことでした。
私は以前、山登りをしていた時期がありました。
仲間は膝にとって登りは何ともないが、下りになると
膝が痛くなって(膝が笑うという表現をします。)辛いと言っていました。
山での下りは重い荷物を持って滑って転ばないために、一歩一歩踏みしめて降りることになります。
しかし、ある人は、荷物を背負っていても坂道を転がるように降りて行きます。
そしてつづら折りのカーブのところでぎゅっとブレーキをかけて減速しながらまた、坂を降りていくのです。
これなども足下を見すぎることで筋肉が疲労してしまって膝に負担がかかるのでしょう。
リズミカルに降りることで膝に負担が軽くなるのですが、
これも階段と同じように転んだら大変なことになりますから用心は必要でしょう。
ヨガの手指ほぐしの場合です。手の平を合わせて指を組む動作をします。いったん手のひらを離して指をずらして組みます。そしてカウントを取ります。
30回くらい数えますが、左右の指がぶつからないように指を組み替えるのです。そして指が互いにぶつかった回数は何回かと聞くと、用心しながらしっかり目で指を見ている人とほどぶつかることが多いようです。
少し難しく行う方法として、手と手の間を1メートルくらい離して、手を見ないで同じように交互に組むのをカウント取ると、難しいのにぶつかる回数が少なくなるのは、記事と同じ内容でしょう。
もっと効率よく、ぶつからないようにするには、その前に指回しをしっかりしておくことです。指の筋肉の反応がよくなってぶつかることがなくなるのです。
当然目は指を見ないことです。頭の体操にもなりますからぜひやってみてください。

台湾で本が出版されました
1昨年夏に刊行された「体が硬い人のためのヨガ」はおかげさまで11刷に達しました。そして当学院の関係の方だけで1000冊が売れ、先日に新たに100冊注文しました。ほんとうに皆様のおかげです。
そしてまたうれしいことに、中国語に訳するという話しもいただき、契約書も1年前に交わし、ようやく台湾で店頭に並んでいるそうです。
企画をいただいて、ライターの方と案を絞り、普段やっている教室での動きを再現すべく討論をしても、変更やボツが重なってようやく、これも出版関係者のプロ意識に支えられて出来上がりました。「水野健二は自分が大好き」と本の中で述べている項目があっても、皆さんのの期待にそえるか不安で、売れないから絶版という恐れも考えていましたがおかげさまで11刷です。「大好き」という呪文は運を良くするものと確信しました。
自分では気が付いていないのですが、あるヨガインストラクターの方が、ヨガポーズを組み立てるのにバイブルになっているということでした。私はその方に、本に書いている動きは単なる一例で、一つ一つの動きをしているときにどこに刺激があったり、気持ち良かったりなど感じることで、次の動きが出てくるものですよ」とコメントしました。普段はマヒして沈黙をしている筋肉が味わっていることで目を覚まして、無意識に、次はここを動かせと指示してくれるのです。
体の柔らかい人、パワフルな人こそ丁寧に自分の体を見つめる機会を作っていただければと思います。最近ユーチューブなどできれいで美しいポーズを作っているお兄さんおねえさんのポーズを観る機会があります。すごいなと感激します。でも、私の周りはおじさん、おばさん、おじいさん、おばあさんが多くなりました。わたしも 「い」の年代です。できる範囲で、かっこわるいけれど気持ちのいい動きを作っていきたいとおもいます。
チーターやワニのように歩く
沖ヨガには強化行法と言って動物のまねのように歩いたり、普段つかわない筋肉を使った動きの行法があります。時にはチャレンジ精神が必要なレンジャーもどきも当時はありました。これらはヨガの標語である「生命力強化」「生命即神」の考えです。生きていること自体不思議な現象であり、かけがえのない、神のご加護である。そして生きていることに喜びを得ていくことが本質だと言う意味です。
今回は四つ足の動物が歩く姿を再現してみます。(教室ではほとんどすることがなくなりました)
チーターは背中のしなやかさのために時速100キロで走るそうです。そのしなやかな背骨をまねした歩き方をやってみましょう。イメージだけで行うのではなく、プロセスを追っていくとそれほど難しくありません。
まず、よつばいです。足裏ならぬ、ひざと手で体を支えます。そして左ひざと左手に体重をかけると背骨はたわみます。次に左ひざで床を押すと背骨を持ちあがるので同時に同側の手(右手)を前に出し、反対の足を前に出します。(動いていないのは左ひざと右手です。)
反対のひざで同じような動きが始まります。すなわち右ひざに重さがかかり、右手にも重さがかかって背骨はたわみます。次に右ひざで床を強く押すと背骨が持ち上がり、同時に同側の手(右手)が前に出て、反対の左ひざが前に出ます。このように次々と背骨は重さをかけられ、そして、もちあげて歩いていくのです。
ワニの歩きは、これと同じパターンですがひざではなく、足を使い、ひざを曲げ、肘を曲げて胸を床に近づけながら歩くので結構きつい動きです。背骨こそ持ち上がりませんが、プロセスを見ていくとできそうです。
胸を床に下げて、左足と左手を近づけておきます。右足と左足は離しておきます。そして左手を前に大きく、伸ばして床につけ、右足を右手の近くにおきます。これを胸を床に近づけて行います。初めの動作の左右逆です。右手を大きく前の伸ばして、左足を左手に近づけます。この動作を繰り返していけばいいのです。
赤レンガ庁舎訪問
天皇陛下のご病気お見舞いに北海道庁(赤レンガ庁舎・旧本庁舎)へ記帳に行きました。ここは24年前、昭和天皇ご崩御にお悔やみの記帳をした時、以来の場所です。
天皇陛下は順調に回復されている報道もあり、記帳所は閑散としていました。ついでにと滅多に入ることのない庁内を見学しました。ここはもう記念館としてのみ使用とのことで、その西側に現在の庁舎が地下2階、12階の建物がそびえています。
明治21年築とのことで、今は北海道の歴史記念文書などが陳列してありました。このブログで紹介した松浦武四郎の大きな肖像がクラーク博士と共に絵画として陳列されていました。
今、札幌は180万都市として栄えていますが100年前までは未開の土地だったのは感慨深いです。
写真は琴似に入植した屯田兵、作られた当時の赤レンガの絵、クラーク博士の島松駅舎での別れ、松浦武四郎の絵はこの下にアイヌの人たちの絵があります。そして現在の赤レンガ庁舎です。